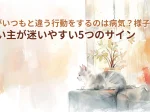年齢別に選ぶ!夏休みに読みたい猫のおすすめ絵本|0歳から小学生までの読み聞かせガイド

子どもたちに人気の「猫 絵本」は、そのかわいらしい猫のキャラクターとやさしいストーリーで心をつかみ、親子の読み聞かせタイムをより豊かにしてくれます。しかし、絵本選びは年齢に合わせた適切な作品を選ぶことが大切です。0歳から小学生まで、成長に応じて理解力や興味の対象が変わるため、それぞれの発達段階に合った猫の絵本を選ぶことで、子どもの感受性や想像力をぐんと育てることができます。
本記事では、「猫 絵本 年齢別」という視点を軸に、0歳、3歳、5歳、そして小学生向けにおすすめの絵本を厳選し紹介していきます。また、読み聞かせのコツや親子時間を充実させるポイントもあわせて解説。夏休みの特別な時間にぴったりな猫の絵本もピックアップしていますので、季節ごとの楽しみ方も見つかります。
子どもの年齢に合った猫の絵本選びに悩んでいる方や、これから読み聞かせを始める方にとって役立つ情報が満載です。絵本を通じて親子の絆を深め、猫好きな子どもがさらに笑顔になるひとときをぜひご一緒に見つけてみませんか。詳しい内容は各年齢別のセクションでわかりやすくご紹介していきます。
「猫 絵本 年齢別」の豊富な知識とおすすめリストで、あなたの読み聞かせ時間がもっと楽しくなることを願っています。ぜひ読み進めてみてください。
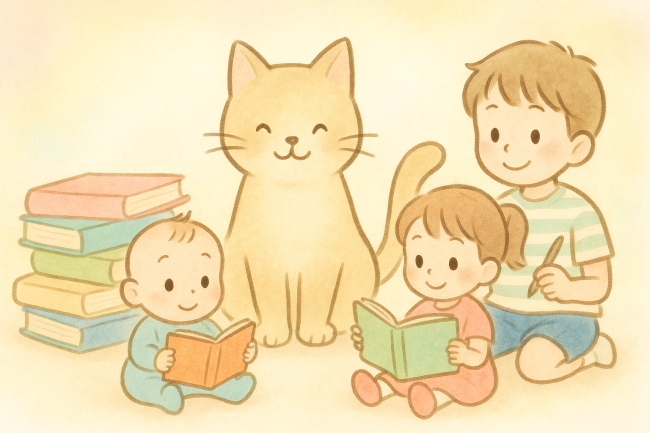
猫の絵本選びの基本|年齢別に押さえたいポイントと読み聞かせのコツ
猫 絵本 年齢別の重要性
猫の絵本は、子供の成長段階に合わせて選ぶことが大切です。年齢ごとに発達する認知能力や感受性は異なり、それにマッチした絵本を選ぶことで、読み聞かせの効果が最大限に引き出されます。
例えば、0歳児には視覚刺激が豊富な絵本が適している一方、幼児期には物語性豊かな絵本が理解力や想像力の育成に役立ちます。小学生になると、自分で読める文字量や内容の幅が広がるため、適切な難易度を選ぶことが必要です。
猫のキャラクターは親しみやすく、子供の情緒を安定させる効果も期待されるため、猫絵本を年齢別に選ぶことは、子供の心身の成長を支える大切なポイントです。
また、年齢別に合わせた絵本選びは、親子のコミュニケーションをより良くし、読み聞かせの時間を楽しく充実させます。季節やイベントごとに変化する子供の興味にも対応しやすくなります。こうした理由から、「猫 絵本 年齢別」というキーワードは多くの親御さんが関心を持つテーマとなっているのです。
0歳~2歳に適した絵本の特徴
0歳から2歳までの乳幼児は、視覚・聴覚・触覚が急速に発達する時期です。この時期の絵本は、シンプルな色彩と形、繰り返しのある表現が特徴です。赤ちゃんの目線に合わせた大きくて見やすいイラストが効果的で、猫をモチーフにした絵本はその可愛らしさから子供の興味を引きつけやすいのが魅力です。
この年齢層向けの猫絵本は、文章が短く、リズム感のある言葉遊びや繰り返しフレーズが多く使われています。繰り返し表現が記憶形成や言語習得の助けとなるため、読み聞かせにも最適です。
さらに、紙の材質にも注意したいところです。丈夫なボードブック形式は、赤ちゃんが口に入れても安全で、ページをめくる楽しさを味わえます。こうした工夫が、初めての「猫 絵本 0歳」体験を安心かつ楽しくするポイントとなります。
この時期には、絵本の色使いも重要です。赤や黄色、青などは赤ちゃんの視覚を引きつける効果が高く、猫の絵がカラフルに描かれていることで、興味を持たせやすくなります。
3歳~4歳に向けた物語性や会話重視のポイント
3歳から4歳になると、子供の言語理解力と注意力が格段に向上します。この時期の猫絵本は、ストーリーがしっかりとしたものを選ぶと良いでしょう。特に、猫同士や子供との会話形式を取り入れた絵本は、自然な言語学習とコミュニケーション能力の向上に貢献します。
会話文が多い絵本は、子供が登場人物の気持ちを理解しやすく、感情の表現にも役立ちます。猫のキャラクターが話しかけてくる構成なら、子供自身が応答したくなるため、読み聞かせの双方向性が生まれます。
また、3歳~4歳は好奇心が旺盛な時期です。読み聞かせの際には、猫の動きやしぐさをマネてみたり、質問を投げかけてみると、子供の参加意欲を高め親子のコミュニケーションが深まります。
この年齢層には、猫の特徴だけでなく、友情や冒険などのテーマを含む物語性の高い絵本がおすすめです。物語の中で、猫が様々な問題を乗り越える姿を見ることで、子供の社会性や問題解決能力の芽生えを刺激します。
5歳~6歳の豊かなストーリーで想像力を育てる方法
5歳から6歳は、言語能力と想像力が飛躍的に成長する時期です。この段階では、より複雑なストーリーや登場人物の心情描写が求められます。猫の絵本でも、物語の深みやテーマ性を重視して選ぶことがポイントです。
この年齢の子供は、自分で読み進める自立心も高まるため、文章量が増え、ますます多様な語彙を含む猫絵本がおすすめです。ストーリーの展開に合わせて、感情の動きを理解しやすい絵本を選ぶと良いでしょう。
想像力を育てるには、猫が主人公の冒険や日常生活を描いた絵本が効果的です。子供は物語を自分の経験と照らし合わせながら、情景を想像し、感情移入していきます。
さらに、読み聞かせでは、「次にどうなるかな?」と問いかけることで、子供の思考力を刺激し、主体的な読書体験を促すことができます。親子ともに楽しめる工夫として、猫の鳴き声や動きをマネする遊びも取り入れると良いでしょう。
小学生向け絵本の選び方と自読みのすすめ
小学生になると、文字を読む力が飛躍的に伸び、絵本も自分で読む時間が増えます。猫絵本でも、文字量が多く、テーマに深みのある作品が適しています。特に、感情表現や倫理的なテーマを含む作品は、子供の価値観形成に好影響を与えます。
小学校低学年向けの猫絵本は、漢字にふりがながついているものや、章立てされたストーリー構成が読みやすくおすすめです。音読に適したリズムや言葉選びを意識した作品も、子供の読解力向上に役立ちます。
この年齢層は自分で読む楽しさを感じることが重要なので、難易度が適切な猫絵本を選びつつ、読み聞かせの時間も継続すると良いでしょう。読み聞かせは子供の理解力をサポートし、親子の時間を豊かにするための効果的な方法です。
また、小学生向けの猫の絵本は、夏休みなど長期休暇に読むことで、読書習慣をつけるきっかけにもなります。季節感やイベントと結びつけた話題の猫絵本を取り入れるのもおすすめです。
読み聞かせ 猫 絵本で親子のコミュニケーションを深める方法
猫の絵本を使った読み聞かせは、単に物語を伝えるだけでなく、親子間のコミュニケーションを豊かにする絶好のツールです。猫の可愛らしい動作や豊かな表情は、子供の感性を刺激し、話を共有する楽しさを促進します。
読み聞かせの際は、子供の反応をよく観察しながら、質問や感想を引き出す工夫をしましょう。たとえば、「この猫はどう思っているかな?」や「もし君がこの猫の立場だったらどうする?」など語りかけることで、対話を深めることが可能です。
また、猫のしぐさをマネするなど体を使った参加型の読み聞かせは、子供の集中力を高めるうえ、親子の絆を強める効果があります。子供が物語に積極的に関わる体験こそが、「年齢別 読み聞かせ」としての最大の魅力と言えるでしょう。
親自身も猫本を通じて子供の成長を感じられるため、読み聞かせは親子時間をより豊かに彩る時間となります。毎日の習慣として取り入れれば、自然と子供の言語力・社会性も育まれていきます。
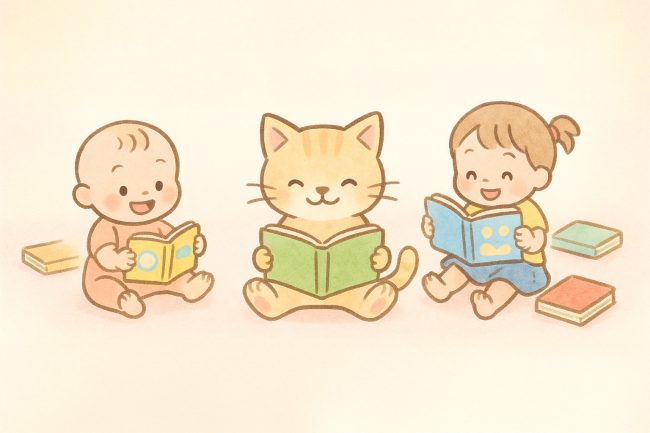
0歳~2歳におすすめ|今注目!猫が主役の新刊絵本
猫 絵本 0歳に最適な作品例と特徴
赤ちゃんや1~2歳の小さな子どもたちにピッタリな「猫」をテーマにした新しい絵本は、可愛らしさや温かみがたっぷり。親子で楽しめるものやプレゼントに最適な新刊・人気作を、記事にまとめました。
めくって遊べる体験型や写真絵本などバリエーション
最近発売された猫絵本は、共感や楽しさに加え、育児の大変さややさしさを描いたストーリー、めくって遊べる体験型や写真絵本などバリエーション豊富です。
「おんぶねこ」や「いた いた みつけた」など2024年・2025年の新刊は“かぶりにくい”点でもおすすめ。定番&人気シリーズも組み合わせて、ぜひ親子の絵本タイムに加えてみてください。
色彩の工夫で赤ちゃんの興味を引きつけるコツ
- おんぶねこ(殿本祐子/2025年3月・講談社)
お父さん猫が子猫のお世話をする、ほほえましい毎日を描いた新作。子育ての大変さもユーモアたっぷりで共感&心温まるストーリーです。 - ねこおうじとうみのいきもの
ねこ王子が海の世界を冒険し、クジラやアザラシなどさまざまな海の生きものたちと出会うお話。イラストたっぷりで、動物の名前や特徴も楽しく学べます。 - ぎょうれつのできるサンドイッチやさん
こねこのココが山のサンドイッチやさんを訪れ、動物たちと一緒に美味しいサンドイッチ作りを体験。食べ物と動物への興味を育てる、やさしい物語です。 - きまぐれレストランのおかし
猫の店長とハシビロコウのウエイターが動物たちへお菓子をふるまうレストラン。みんなが好きなスイーツが登場し、親子のやりとりやごっこ遊びにもぴったりのお話。
ロングセラー・定番の猫絵本
- ちいさなねこ(石井桃子/福音館書店)
小さな猫の冒険や、親子のきずなを描いた心あたたまる名作。自我が芽生える頃のお子さまにもぴったりです。 - ノラネコぐんだん シリーズ(工藤ノリコ/白泉社)
ワルかわいいノラ猫たちが繰り広げる愉快な冒険。2024~2025年にも新作や派生絵本が続々登場中。めくりや探しあそび要素もあり幅広い人気を集めています。 - だっこ むぎゅー(いりやまさとし)
赤ちゃん猫の「だっこ」にほっこり。可愛いイラストと愛情たっぷりの世界観で、プレゼントにも喜ばれる絵本です。
新刊&注目作品(2024~2025年)
| タイトル | 出版年 | 特徴・内容 |
|---|---|---|
| おんぶねこ | 2025年 | お父さん猫と子猫の日常を描く心温まる新作。育児のユーモアや優しさに満ちたストーリー。 |
| ねこおうじとうみのいきもの | 2025年 | ねこ王子が海の世界を冒険し、クジラやアザラシなどさまざまな海の生きものたちと出会うお話。イラストたっぷりで、動物の名前や特徴も楽しく学べます。 |
| ぎょうれつのできるサンドイッチやさん | 2022年 | こねこのココが山のサンドイッチやさんを訪れ、動物たちと一緒に美味しいサンドイッチ作りを体験。食べ物と動物への興味を育てる、やさしい物語です。 |
| きまぐれレストランのおかし | 2021年 | 猫の店長とハシビロコウのウエイターが動物たちへお菓子をふるまうレストラン。みんなが好きなスイーツが登場し、親子のやりとりやごっこ遊びにもぴったりのお話。 |
定番で長く親しまれている猫絵本
| タイトル | おすすめポイント |
|---|---|
| ちいさなねこ | 子猫の冒険と親子のきずなを描いた名作。“安心”と“チャレンジ”を感じられるストーリー。 |
| ノラネコぐんだん シリーズ | いたずら好きな猫たちが繰り広げる笑いの絶えない人気シリーズ。探し遊び・ページ探しも楽しい。 |
| だっこ むぎゅー | 赤ちゃん猫の「だっこ」に心がほぐれる愛情たっぷりの絵本。親子のふれあい読み聞かせにも好評。 |
選び方のポイント
- 2024~2025年の新刊や写真絵本は“かぶりにくい”ギフトとしておすすめ。
- 優しいイラストや短いストーリー、リズムが楽しい本は0~2歳でも飽きずに楽しめます。
- “親子”“だっこ”“お出かけ”“わくわく感”など、赤ちゃん期にぴったりのモチーフが多いです。
猫絵本は愛らしさ・共感・成長・笑い、いろんな気持ちが詰まったジャンル。ぜひ最新刊やお気に入りの一冊を探して、豊かな絵本タイムを楽しんでください。
読み聞かせのタイミングと親子時間の工夫
読み聞かせのタイミングは、赤ちゃんの機嫌や生活リズムに合わせることが大切です。特に寝る前の静かな時間や、授乳後のリラックスタイムに猫絵本を使うと、親子の絆も深まりやすくなります。
短時間で終わるシンプルな猫絵本を選び、あまり詰め込みすぎないのがコツです。赤ちゃんが興味を示さなくなったら無理に続けず、自然な形で読み聞かせタイムを終了しましょう。
また、読み聞かせの際は、親の声の抑揚や表情が赤ちゃんの集中を促します。猫の鳴き声を真似たり、ページの猫の絵を指でなぞるなどして、やさしいスキンシップを交えることもおすすめです。
こうした工夫で「親子時間 絵本」としての価値が高まり、乳幼児期の情緒安定と健やかな発達を支えます。猫絵本は、0歳~2歳の子供と親が楽しく触れ合うための最高のアイテムと言えるでしょう。

3歳~4歳におすすめ|ストーリーやシリーズで楽しめる猫絵本
3歳~4歳の子供は言葉の理解がぐんと深まり、感情表現も豊かになる時期です。この年代に合った猫の絵本は、物語性がしっかりしていて、親子での会話が広がる作品を選ぶのがポイントです。感性が育ち、自己表現やコミュニケーションの基礎が形成されるため、登場人物のセリフを真似したり、物語に登場する猫の行動について話し合うことで、語彙力や社会性を育むことに繋がります。
- ノラネコぐんだん シリーズ(工藤ノリコ/白泉社)
いたずら好きなノラネコたちがさまざまなお店でドタバタ劇を繰り広げる大人気シリーズ。例えば『ノラネコぐんだん おすしやさん』や、2025年新作の『ぺこぺこキャンプ』など、どれから読んでも楽しいです。 - どすこいみいちゃんパンやさん(町田尚子/ほるぷ出版)
おすもうさんのような猫・みいちゃんがパン作りに奮闘。愉快なリズムとイキイキした猫の動きが魅力です(4歳~おすすめ)。 - 100まんびきのねこ(ワンダ・ガアグ/福音館書店)
とても多くの猫が登場するちょっと不思議で長く愛されている世界的名作です。 - ちいさなねこ(石井桃子/福音館書店)
子猫の冒険と親子の絆を描いた、3歳から読み聞かせにぴったりのロングセラー。 - ねこいる!(たなかひかる/ポプラ社)
「いる?いない?」と繰り返し登場する猫の存在にドキドキワクワク。ユーモアと参加型の面白さがいっぱい。
個性派・新しいビジュアルの猫絵本
- ねこひげ ぴぴん(ほんまちひろ 文/ミース・ファン・ハウト 絵/西村書店)
22匹の猫たちの表情とユニークな動きが、カラフルで海外らしいタッチで描かれます。みんなで踊ったり遊んだり、想像が広がる1冊。2024年3月刊。 - おんぶねこ(殿本祐子/講談社)
おとうさん猫と子猫の日常。ワンオペ育児ユーモアや家族のあたたかさが伝わるストーリー(3歳~)。
まとめ表
| タイトル | 特徴・ポイント | 目安年齢 |
|---|---|---|
| ノラネコぐんだん シリーズ | 笑える!ドタバタ冒険/リズム感 | 3歳~ |
| どすこいみいちゃんパンやさん | パン作り×ユーモア×猫 | 4歳~ |
| 100まんびきのねこ | 世界的名作/たくさんの猫たち | 3歳~ |
| ちいさなねこ | 子猫の冒険/親子愛/ロングセラー | 3歳~ |
| ねこいる! | いる?いない?繰り返しの楽しさ | 3歳~ |
| ねこひげ ぴぴん | 22匹の猫の表情/カラフル絵 | 3歳~ |
| おんぶねこ | おとうさん猫の奮闘/家族のあたたかさ | 3歳~ |
選び方のポイント
- シリーズものや人気作は、ストーリーが分かりやすいので、お話の理解が深まる時期の3~4歳に最適です。
- 「ねこいる!」や「ねこひげ ぴぴん」などは、ページをめくるたびに参加したくなる仕掛けや色彩が魅力。
- 「100まんびきのねこ」や「ちいさなねこ」は、やさしいタッチ・冒険や家族のあたたかさが心に残ります。
新作・人気作は書店や図書館、オンライン書店で見つけやすいので、ぜひ気になったものを手に取ってみてください。猫愛にあふれる絵本タイムが楽しめます
子どもの感情を育む読み聞かせのテクニック
3~4歳児の感情はまだ未発達ですが、猫の絵本を通じて様々な気持ちを体感させることが可能です。絵本の中で猫の嬉しい、悲しい、怒った表情を丁寧に読み取り、子供自身の気持ちについても声をかけてあげましょう。
たとえば、「猫ちゃんはどうして悲しいのかな?○○ちゃんも悲しかった時はあるかな?」と問いかけることで、自己認識力と他者理解力が育ちます。こういった対話を繰り返すうちに、表現の幅が広がり気持ちを伝えられる子供に成長します。
絵本の読み聞かせは、感情の名前を教える絶好の機会。たとえば「ねこちゃんは嬉しくてしっぽをふってるね」と言いながらしっぽの仕草を真似すると、抽象的な「嬉しい」という感覚を具体的に覚えやすくなります。
これらのテクニックは、猫好きの子供にとって特に効果的。猫の可愛らしい表情や動作を使って感情を伝えることで、親子のコミュニケーションが深まり、子供の自己肯定感が高まります。
猫好き 絵本としての魅力と子供の興味を引くポイント
この年齢の子供は猫の動きや仕草に強い興味を持つため、リアルな描写だけでなくコミカルな猫キャラクターが登場する作品も好まれます。猫の「にゃーん」という声やじゃれあう様子は、子供の好奇心を刺激し、絵本への没入感を高めます。
例えば、『おしゃべり猫とふしぎなぼうし』は、猫が魔法の帽子をかぶっていろんな動物に変身するお話です。子供は変身するたびに「次はどんな猫になるの?」と想像し、物語の先を楽しみにすることができます。
また、猫が「ねこパンチ」や「お昼寝ポーズ」で表現するユーモアあふれる場面は、子供の笑顔を誘い、絵本への親近感が強まります。こういった遊び心のある猫絵本は、猫好きの子供にとって特別な一冊になるでしょう。
こうした猫絵本は子供の興味を維持すると同時に、親子時間を楽しくする大きな役割を果たします。読み聞かせの時間を季節ごとにテーマを変えて楽しむのもおすすめです。

5歳~6歳におすすめ|想像力を育む豊かなストーリー猫絵本
5歳~6歳になると、子供の認知力や語彙力が著しく伸び、物語の背景や登場人物の気持ちを理解する能力が高まります。この時期は、想像力を豊かに刺激する長めのストーリーや、登場人物の心情に深く迫る内容が適しています。猫を主人公にした絵本には、ファンタジー要素や友情などテーマ性の強い物語が多く、子供の感受性や思考力を豊かに育みます。
さらに、5~6歳の子供は自分で絵本を読む練習も本格化する頃です。物語性の豊かな猫絵本なら、構成がしっかりしているため読み応えがあり、繰り返し読むことで文章の理解が深まります。
ストーリー・しかけが楽しめる絵本
- 100万回生きたねこ(佐野洋子)
永遠の名作。「生きること」「愛すること」の哲学も感じられる深い物語で、親子で何度も読み返したくなる一冊。 - ノラネコぐんだん シリーズ(工藤ノリコ)
大人気のドタバタ冒険ストーリー。ワンワンちゃんの店でおきる失敗や、毎回お決まりの展開に子どもが爆笑。 - 11ぴきのねこ(馬場のぼる)
個性あふれる11匹のネコたちが力を合わせて冒険する長年愛されるシリーズ。何度読んでも飽きません。 - なまえのないねこ(竹下文子/町田尚子)
自分の「なまえ」を探して街を歩き回る猫の成長とさがしものストーリー。やさしさも勇気も感じる一冊。 - ちいさなねこ(石井桃子)
好奇心いっぱいの子猫が冒険し、親子の愛情を描いた定番絵本。ストーリー性が高く、この年齢にぴったり。 - ヤマネコとアザラシちょうさだん(五十嵐美和子)
海をきれいにする大作戦!ヤマネコ&アザラシの活躍で夢中になる自然とSDGsも学べる一冊。
参加型&コミカルな絵本
- ねこいる!(たなかひかる)
ねこは“いるのか、いないのか”という繰り返しギャグがたまらない、子どもの観察力も伸ばす話題作。 - ねこのラーメンやさん
おちゃめな猫たちがラーメンつくりに奮闘。シュールでクセになる世界観が人気。
ひと味違う!表現力にあふれる猫絵本
比較・選びやすい一覧
| タイトル | 特徴 | 雰囲気 |
|---|---|---|
| 100万回生きたねこ | 深い物語・名作 | 感動・余韻 |
| ノラネコぐんだんシリーズ | ドタバタ冒険・爆笑 | ユーモア |
| 11ぴきのねこシリーズ | 仲間との冒険、リーダーシップ | 楽しい |
| なまえのないねこ | やさしさ・成長・自分さがし | しみじみ |
| ちいさなねこ | 子猫の冒険と家族の愛 | ホッと安心 |
| ヤマネコとアザラシちょうさだん | SDGsテーマ・協力 | ワクワク |
| ねこいる! | ギャグ・参加型・観察あそび | 爆笑 |
| おんぶねこ | 家族・共感・新刊 | あたたかい |
選び方のヒント
- 「ストーリー性重視」「冒険・仲間」「コミカルな参加型」など、子どもの関心タイプに合わせていろいろ選べます。
- シリーズものは、繰り返しの展開や成長を味わうのにおすすめ。
- 贈り物や図書館利用でも見かけやすい作品多数です。
どれも5歳~6歳らしい想像力や好奇心を刺激し、親子の読書タイムがもっと楽しくなるでしょう。まずは気になった作品の表紙や中身を見て、子どもと一緒に選ぶのもおすすめです
ストーリーの深みと創造力の育成ポイント
この年齢の子供はストーリー全体の起承転結を理解できるため、物語の構成がしっかりしている猫絵本は学びの宝庫です。起承転結を意識して読み聞かせることで、物語を分析する力や表現力の向上につながります。
さらに、猫のキャラクターの行動や心情に注目しながら読むことで、共感力や自己理解も促せます。たとえば、「にゃんたはなぜこの時に悲しかったのかな?」と感情に焦点を当てる問いかけは、創造力と感受性を同時に育みます。
加えて、猫の不思議な能力や特別な体験をテーマにした物語は、子供の仮説立てや想像する力を高める絶好の教材です。解釈の幅が広いため、親子の会話が弾むことも楽しみの一つです。
物語の展開で子どもの理解力と語彙を増やす方法
物語を読み進める際には、随所でキーワードや場面について説明を加えることで、難しい単語や表現も自然に身につきます。たとえば、猫の感情を表す「切なさ」や「期待感」といった言葉を説明しながら読み聞かせると、語彙力の向上に効果的です。
また、一度読んだ後に物語の内容を振り返る時間を設け、「どの場面が一番印象的だった?」と質問することで、記憶力と文章理解力がさらに磨かれます。こうした反復読み聞かせは夏休みの長期休暇に特におすすめで、集中して物語を味わう貴重な機会となります。
読み聞かせの中で、「もし自分が猫だったらどうする?」と問いかける方法も、想像力だけでなく論理的思考力の発達に役立ちます。日常生活の中で感じたことを物語と照らし合わせることで、子供の世界観が豊かになります。
親子での読み聞かせ 夏休み 絵本 おすすめ作品も紹介
夏休みの期間は、ゆっくりと長めの絵本を楽しむ絶好の機会です。夏休み中にじっくり読み聞かせできる猫絵本には、季節感や冒険感のある作品を選ぶと、より親子時間が豊かになります。
夏休みの絵本選びでは、物語の長さや難しさ、そして季節感のバランスを考えながら、親子で一緒に楽しむ工夫をしましょう。たとえば、夕方の涼しい時間に読み聞かせの時間を作るなど、読み聞かせのルーティン化が親子関係の強化にもつながります。

小学生向け|自分で読める猫の絵本&人気の新作・夏休みおすすめ
小学生になれば、自力で読む楽しみが増え、より長く複雑な猫の物語を味わえるようになります。この時期は児童書のジャンルにも踏み込んで、読み応えのあるストーリーと多彩な表現力を駆使した作品を選ぶと良いでしょう。自分で読む絵本としては文字の配置や文章量が子供のレベルに合致しているものが理想的です。
猫が大好きな小学生にぴったりな本は、ストーリー性・冒険・笑いや感動、そして動物たちとの絆を深めるものまで幅広く揃っています。近年注目の新作から定番まで、読み応えがあるおすすめを紹介します。
物語・感動を味わえる絵本・児童書
- びりっかすの子ねこ
弱々しい子猫が、挑戦と成長を経て“自分だけの特別な才能”を見つけていく物語。努力の大切さや、周囲の支えのありがたさを学べる一冊。 - 100万回生きたねこ
読み継がれる名作。さまざまな人生を生きた猫が、最後に「本当の愛」を知る深いストーリー。命や家族の意味をじっくり考えさせてくれます。 - なまえのないねこ
名前のない野良猫が、自分にぴったりの名前を探す旅に出る心温まる絵本。自分らしさや存在の大切さへの気づきがテーマです。
シリーズ・ユーモア・冒険にワクワク
- ノラネコぐんだん シリーズ
お店やキャンプ、ピザ作りなど、ワルかわいいノラ猫たちの集団が巻き起こす大冒険が人気。探し絵や迷路要素、繰り返しの展開で楽しめます。 - 11ぴきのねこ シリーズ
個性派ぞろいの11匹が力を合わせて冒険!ダイナミックな展開とコミカルな挿絵が小学生にも大人気。 - 100ぴきかぞく ゆうえんちへいく
100匹の猫の家族たちが大集合!ページごとにお気に入りの子を探して楽しめる絵探しタイプ。リピート読みにも◎。
動物好き・読書が苦手な子にもおすすめ
- しばいぬチャイロのおはなし シリーズ
柴犬チャイロと猫のシロが夜の大冒険へ。短編形式なので少しずつ読め、動物好きな子や読書初心者にもおすすめです。 - ねこいる!
“ねこはいる?いない?”繰り返し遊べるギャグ絵本。観察力とユーモアを刺激し、盛り上がる参加型。
体験・分類タイプ
比較・選びやすいまとめ表
| タイトル | 特徴・ポイント | おすすめ年齢 |
|---|---|---|
| びりっかすの子ねこ | 成長物語・努力・家族愛 | 小学1~4年生 |
| 100万回生きたねこ | 哲学的・命や愛について | 小学2年~上級生 |
| なまえのないねこ | 自分探し・やさしさ | 小学1~3年生 |
| ノラネコぐんだん シリーズ | 笑い・冒険・繰り返し | 小学1~4年生 |
| 11ぴきのねこ シリーズ | 仲間・冒険・ユーモア | 小学1~3年生 |
| 100ぴきかぞく ゆうえんちへいく | 探し絵・図鑑要素 | 小学1~3年生 |
| しばいぬチャイロのおはなし | 夜の冒険・短編集 | 小学1~2年生 |
| ねこいる! | 参加型・観察あそび | 小学1~2年生 |
| ねこのずかん 家ねこと野生ねこ | 図鑑・知識・猫好き向け | 小学1~6年生 |
小学生向け猫絵本 選び方のポイント
- 「感動・成長」の物語派、「ドタバタ冒険」のシリーズ派、「知識図鑑」「探しもの遊び」など、興味や性格に合わせて選ぶと◎
- シリーズものや繰り返し展開は読書習慣が定着しやすく、親子の読書タイムにもぴったり
- プレゼントなら、“新刊”や探し絵・迷路系絵本を選ぶと話題になりやすい
猫が主役の本は、読書を通じて「やさしさ」「勇気」「仲間」「挑戦」など豊かな心をはぐくむきっかけにもなります。気になる作品からぜひ手に取ってみてください
夏休み 絵本 おすすめポイントと親子で楽しむコツ
夏休みの長期休暇は、小学生にとって自由に読書時間を確保できる貴重な時期です。そこでおすすめの猫絵本は、集中力が続く構成かつ物語に深みがあり、親子で話し合いながら読み進められる作品です。
読み聞かせのコツとしては、子供の読書ペースに合わせて質問をしたり、キャラクターの心情を一緒に考えたりすることが挙げられます。たとえば、「ねこがこんなふうに感じたのはなぜだろう?」と問いかけ、子どもの意見を引き出すことで、より深い理解と自己表現が促されます。
さらに、読書記録をノートにまとめたり、読んだ作品の感想を書いたりするのも良い習慣です。親子で感想を共有することで、読書が一過性のイベントではなく生活の一部となり、猫好きの子供にとっては継続的な楽しみになるでしょう。
子供向け 猫の本の活用法と習慣化する読み聞かせ術
小学生になると、親子の読み聞かせは自律的な読書習慣形成の助けになります。猫の絵本を活用する際は、「読書の時間」を決めて毎日続けることが鍵です。たとえば、寝る前の15分間は必ず絵本の時間にするなど、ルール化が有効です。
また、通学や外出時に猫絵本の電子版を利用する方法も現代的で便利です。スマートフォンやタブレットで手軽に読み進められるため、隙間時間を活用して読書量を増やせます。
親が感想や好きなシーンを話題にすると、子供は自分の気持ちを整理しやすくなります。猫のキャラクターへの感情移入も深まり、読書へのモチベーションも持続します。
このように、小学生向けの猫絵本は物語の深さを活かした読み聞かせと、自主的な読書習慣づくり双方からアプローチすることで、豊かな心と知性を育てられるのです。

年齢に合わせた猫の絵本選びで、親子の時間をより豊かに楽しもう
猫の絵本はその愛らしいキャラクターと多彩なストーリーで、子どもの成長段階に寄り添う素晴らしい教材となります。年齢別に適した絵本を選ぶことで、子どもの発達に合った刺激や理解を促し、読み聞かせの効果を最大限に引き出せるのが何よりの魅力です。
0歳から2歳の赤ちゃんには、繰り返し表現や鮮やかな色彩の絵本が最適です。これにより、言葉の習得や視覚的興味を育てることができます。3歳から4歳になると、会話が多い物語性のある猫絵本が子どもの感情や想像力を刺激し、親子のコミュニケーションも自然に深まります。
さらに5歳から6歳になると、より複雑なストーリーや豊かな表現を含んだ猫絵本が、子どもの理解力や語彙力の底上げに役立ちます。読み聞かせの工夫として、物語の展開に合わせて問いかけや感想を共有することで、子ども自身の考えを引き出す効果も高まります。
小学生になると、自分で読む楽しみを経験し始めるので、ネイティブな表現が豊富で、好きな猫キャラクターが活躍する作品を選ぶと良いでしょう。夏休みなどの長期休暇には、親子で一緒にじっくり読み進められる読み聞かせの時間を設けることが、より深い絆作りにもつながります。
どの年齢でも共通して大切なのは、子どもの興味関心に寄り添い、無理なく楽しい読書習慣を身に付けられる環境づくりです。猫絵本は、物語を通じて親子の会話や感情の交流を促進し、子どもの情緒面の発達を支える素敵なツールとして機能します。
初めて猫の絵本を手に取る際は、図書館や書店で実際にページをめくりながら、子どもの反応を観察して選ぶことがおすすめです。また、信頼できる児童書出版社の推薦リストやレビューを参考にすることで、良質な作品に出会いやすくなります。
これから猫絵本を通して読み聞かせを始める方も、すでに親子で楽しまれている方も、ぜひ年齢別のポイントを意識して作品選びをしてみてください。そうすることで読み聞かせの時間がより豊かで意味深いものとなり、子どもの感性や言語能力だけでなく親子の絆も自然と深まるでしょう。
猫好きの子どもたちの心をつかむ絵本選びは、読み聞かせの習慣化と合わせて親子双方の幸福感を高める大切なステップです。今後も子どもの成長や興味の変化に合わせて新しい猫絵本を取り入れ、家族の笑顔溢れる時間を積み重ねていただければ幸いです。
投稿者プロフィール

- 「ねこびとライター!ももこ」プロフィール
猫愛にあふれるライターです。
過去に保護猫活動の経験を持ち、猫たちの命を守るために全力を尽くしてきました。自宅では、あまあまの黒猫「まめ」とハチワレ「くるみ」の2匹とともに楽しい毎日を過ごしています。
現在はライターとしての仕事をしていて主に猫に関する記事を執筆しています。
また、ライターの仕事とは別に猫に関連する場所への旅行も好きです。新たな猫の友達と出会い、世界中の猫カルチャーを探求することことを目指しています!
最新の投稿
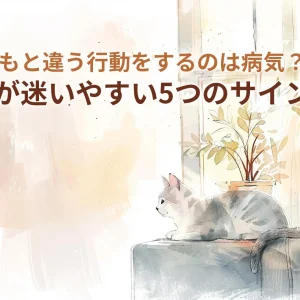 特集2026年1月14日猫がいつもと違う行動をするのは病気?様子見?飼い主が迷いやすい5つのサイン
特集2026年1月14日猫がいつもと違う行動をするのは病気?様子見?飼い主が迷いやすい5つのサイン 特集2026年1月12日猫好きのためのバレンタインチョコ選び 2026
特集2026年1月12日猫好きのためのバレンタインチョコ選び 2026 特集2025年12月24日【2025年最新】猫翻訳アプリTOP3徹底比較|専門家が警告する「精度の真実」と正しい活用法
特集2025年12月24日【2025年最新】猫翻訳アプリTOP3徹底比較|専門家が警告する「精度の真実」と正しい活用法 特集2025年12月10日年末年始のご挨拶に贈りたい「猫スイーツ特集」
特集2025年12月10日年末年始のご挨拶に贈りたい「猫スイーツ特集」